平成22年度以後の個人住民税(市・県民税)の主な改正点
更新日:2018年3月1日
個人市・県民税の課税について
上場株式等の譲渡益・配当に対する課税方法が見直されました
1 上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長(3年間)
平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間に行われる譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して、申告分離課税により課される個人住民税の所得割の税率については、3%の軽減税率とする特例措置が、平成23年12月31日まで延長されました。
本則税率5%となります。(平成25年度の税制改正により更に2年間延長し、平成25年12月31日まで延長されました。)。
| 年度 (年分) |
平成21年度 (平成20年分) |
平成22年度 (平成21年分) |
平成23年度 (平成22年分) |
平成24年度 (平成23年分) |
平成25年度以降 (平成24年分以降) |
|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% (住民税3%、 所得税7%) |
【原則】 20%(住民税5%、所得税15%) |
20% (住民税5%、所得税15%) |
||
| 【特例措置】 ●上場株式等の配当(100万円以下の部分) 10%(住民税3%、所得税7%) ●上場株式等の譲渡益(500万円以下の部分) 10%(住民税3%、所得税7%) |
|||||
↓
| 年度 (年分) |
平成21年度 (平成20年分) |
平成22年度から平成26年度まで (平成21年分)(平成25年分) |
平成27年度以降 (平成26年分以降) |
|---|---|---|---|
| 税率 | 10% (住民税3%、 所得税7%) |
10% (住民税3%、所得税7%) |
20% (住民税5%、 所得税15%) |
2 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において、当該上場株式等に係る配当所得の金額については、申告分離課税を選択できる制度が創設されました。
この場合において、申告する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用とすることとし、総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。
| 年度 (年分) |
平成21年度まで (平成20年分まで) |
平成22年度(平成21年分)から 平成26年度(平成25年分)まで |
平成27年度以降 (平成26年分以降) |
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 累進税率(住民税10%、所得税5~40%) | ||
| 申告分離課税 | ー | 10% (住民税3%、所得税7%) |
20% (住民税5%、所得税15%) |
3 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設
上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税が選択できるようになりました。平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間は軽減税率が適用され、申告分離課税を選択した場合の税率は10%となります。申告分離課税を選択することで、配当控除は受けられなくなりますが、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が可能になりました。
(平成25年度の税制改正により更に2年間延長し、平成25年12月31日まで軽減税率が適用になりました。)。
※申告分離課税を選択した場合の平成26年1月1日以降の税率は20%(住民税5%、所得税15%)です。
| 平成21年度 (平成20年分) |
平成22年度 (平成21年分) |
平成23年度以降 (平成22年分以降) |
|---|---|---|
| 損益通算できない | 確定申告により損益通算できる | |
| ー | 源泉徴収選択口座において損益通算できる | |
土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地を譲渡した場合(所有期間が5年を超えるものに限る)には、1,000万円(当該譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得金額)の特別控除が適用されます。
《個人住民税の課税に影響があるのは平成28年度以降》
個人住民税における住宅ローン特別控除の創設
1 住民税における住宅借入金等特別税額控除について(平成21年~平成26年3月までに入居された人)
平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年までに入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、平成22年度から、個人住民税の所得割から控除する制度が創設されました。この制度の適用を受けるための市への申告書の提出は「不要」です。(平成25年度税制改正により、住宅ローン特別控除は平成21年から平成29年まで延長されました。但し、5%控除は平成26年3月まで延長。くわしくはこちら)
※申告書の提出は「不要」ですが、給与の人は、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がなければ計算することができません。
また、平成21年中に入居された人など所得税の確定申告により住宅ローン控除をされる人も、確定申告書第二表に「居住開始年月日」の記載がなければ計算することができませんので御注意ください。
計算方法
次の(1)又は(2)のいずれか少ない額を個人住民税の所得割から控除します。
(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
控除期間
最長10年
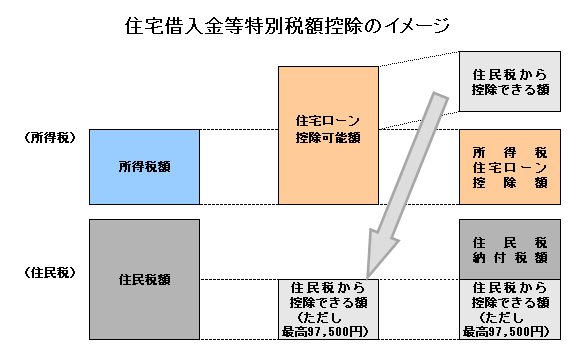
住宅ローン控除イメージ
2 住民税における住宅借入金等特別税額控除について(平成11年~平成18年までに入居された人)
平成11年から平成18年までに入居した人は、市民税県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより控除していましたが、平成22年度分から市への申告書の提出は「不要」になりました。
※平成22年度分からの申告書の提出は「不要」ですが、給与の人は、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がなければ計算することができません。
所得税の確定申告により住宅ローン控除をされる人も、確定申告書第二表に「居住開始年月日」の記載がなければ計算することができませんので御注意ください。
平成22年度からの計算方法
1の平成21年~平成25年までに入居された人と同じ計算方法です。
対象者
(1)平成11年から平成18年末までに入居した人
(2)所得税から控除しきれず、住宅ローン控除可能額が残っている人
(3)住民税において、所得割が課税されている人
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230


















