受動喫煙防止対策について
更新日:2024年1月26日
「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)

望まない受動喫煙の防止を図るための必要な措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定が、平成31年(2019年)1月24日より順次施行されています。
詳細については、下記の厚生労働省ホームページ等の情報をご覧ください。
【受動喫煙対策コールセンター(厚生労働省委託)について】
TEL 0120-251-262 (令和5年4月1日から電話番号が変わりました)
![]() 改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日改正)(PDF:890KB)
改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日改正)(PDF:890KB)
主な改正法の内容及び留意点は、以下のとおりです。
飲食店のみなさまへ(飲食店における受動喫煙対策について)
改正健康増進法が施行され、飲食店を含む多くの人が利用する施設(第二種施設)において、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。このことについて、必要な情報をまとめていますので、下記のファイルをご覧ください。
各種様式のダウンロード
喫煙専用室を設置する場合・・・(喫煙室では喫煙のみ可)
※上記「飲食店のみなさまへ」のB
加熱式たばこ専用の喫煙室を設置する場合(喫煙室では飲食等も可)
※上記「飲食店のみなさまへ」のB
![]() 標識例(加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に掲示)(外部サイト)
標識例(加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に掲示)(外部サイト)
経過措置として、店内で喫煙可とする場合(店内で喫煙しながら飲食可)
喫煙可能室について
飲食店については、令和2年4月1日時点で営業しており、客席面積100平方メートル以下かつ個人又は中小企業(資本金5,000万円以下)の既存店舗のみ、喫煙可能室の設置(1)や店舗全体を喫煙可(2)とすることができます。
この場合、令和2年4月1日までに高松市保健所に届出を提出していただく必要があります。
令和2年4月2日以降に新規に開店する飲食店は、客席面積等にかかわらず喫煙可能室の設置はできません。
※上記「飲食店のみなさまへ」のC
喫煙可能室に関する届出について
![]() 喫煙可能室設置施設届出書の届出事項を変更したとき(ワード:40KB)
喫煙可能室設置施設届出書の届出事項を変更したとき(ワード:40KB)
喫煙目的施設について
喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙する場所を提供することを主目的にする施設を指します。
具体的な施設は次の3種類です。
(1)公衆喫煙所:施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするもの。
(2)喫煙を主目的とするバー・スナックなど
(3)店内で喫煙可能なたばこ販売店
喫煙目的施設の規制内容
屋内の全部又は一部の場所に、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置することができます。
なお、「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等の営業を行うことが可能となります。
![]() バーやスナックなどを経営している皆さまへ(PDF:103KB)
バーやスナックなどを経営している皆さまへ(PDF:103KB)
事業所のみなさまへ
飲食店と同様、第二種施設であり、建物内禁煙となります。喫煙専用室を設置する場合、標識の掲示が義務付けられます。
【受動喫煙防止対策に関する各種支援事業】
飲食店を含む事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる支援制度が整備されています。
受動喫煙防止対策助成金:職場での受動喫煙を防止するために喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成する制度です。
(1)従業員がいる事業所の場合
※詳細は、下記のホームページをご覧ください。
![]() 厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策助成金」(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策助成金」(外部サイト)
(2)生活衛生関係営業の事業主であって、労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業主
(いわゆる「一人親方」)の場合
※詳細は、下記のホームページをご覧ください。
![]() 公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター「生衛業受動喫煙防止対策助成金」(外部サイト)
公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター「生衛業受動喫煙防止対策助成金」(外部サイト)
受動喫煙防止対策に係る相談支援
職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じる(希望によって、事業場に訪問して助言)等
【お問い合わせ先】
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 受動喫煙防止対策相談窓口 050-3537-0777
(令和5年度厚生労働省委託事業)
喫煙をする際の配慮義務に関する事項
喫煙をする人は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない。
具体例
・できるだけ、周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮する。
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、特に喫煙を控える。
など
喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項
多数の人が利用する施設を管理する人は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう、配慮しなければならない。
具体例
・施設の出入口付近や、利用者が多く集まる場所には設置しない。
・喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について、周辺の通行量や状況を勘案して、受動喫煙が生じない場所とする。
など
受動喫煙とは
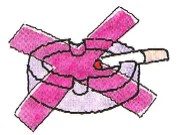
定義
人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること。
受動喫煙による健康への悪影響
流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等の生理学的反応や慢性影響として肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇が示されています。
また、受動喫煙の煙の中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含まれており、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり、特に親の喫煙によって、子どもの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど様々な報告があります。
たばこと健康について考えてみませんか
加熱式たばこについて
![]() 加熱式たばこについての詳細はこちらをご覧ください(外部サイト)
加熱式たばこについての詳細はこちらをご覧ください(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879


















