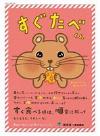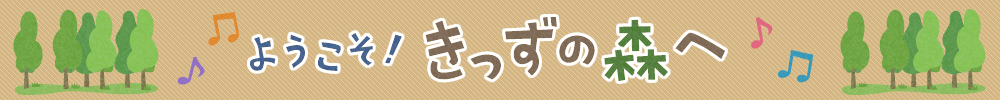このページでは、皆さんに知っていて欲しい大切なことをまとめています。
問い合わせ:生活衛生課(電話:087-839-2865) 感染症対策課(電話:087-839-2870)
感染性胃腸炎(ノロウィルス)に気を付けましょう
ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は1年を通して発生しますが、
特に冬季に流行します。感染力が非常に強く、
子どもや高齢者は重症化することもあります
(食品から)
1.ノロウイルスに汚染された二枚貝などを加熱不十分の状態で食べる
2.調理従事者などの手や調理器具を経て、二次汚染された食品を食べる
3.汚染された井戸水などを消毒不十分で摂取する
(人から)
1.ノロウイルスが含まれる便や吐物から人の手を介して、ウイルスが口に入る(二次感染)
2.ノロウイルスが含まれる便や吐物の飛沫を吸い込む
1.トイレの後や調理、食事の前は、石けんと流水で丁寧に手を洗いましょう
2.加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱することが重要です
ノロウイルスに汚染されている可能性のある二枚貝などは、
中心部の温度が85度から90度までで90秒以上加熱しましょう
3.調理器具やシンクはしっかり洗浄、消毒しましょう
4.吐物や便の処理をする時は、ウイルスが飛び散らないよう静かに拭き取り、
次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう
※使い捨てのエプロン、手袋、マスクを着用
5.感染が疑われる場合は、入浴は最後にして、タオルなどの共用は避けましょう
問い合わせ: こども女性相談課(電話:087-839-2384)
家事や家族のお世話をしているあなたへ

おうちでのお手伝いや家族のお世話で、勉強する時間がない、
友達と遊べない、学校に行けない、気持ちが落ち込む、
いつも疲れている、など困っていることはありませんか?
あなたの周りに、助けてくれる人や相談できる人はいますか?
あなたの困っていることを一緒に考えるための相談窓口があります
相談についての秘密は守ります
何を話したらいいかわからなくても大丈夫!
まずは、お話を聞かせてくださいね
相談先:高松市役所こども女性相談課
電 話:087-839-2384
※月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています
(祝日と12月29日から1月3日の間は除きます)
メール:kojyo_soudan@city.takamatsu.lg.jp
ヤングケアラーを知っていますか?
その他の相談窓口などの情報はこちらです。
問い合わせ:子育て支援課(電話:087-839-2354)
「こども・若者のご意見箱」の設置について

高松市ホームページ内に「こども・若者のご意見箱」を
設置します
子どもや若者が、高松のまちに対して思っていることや
感じていることを把握する仕組みとして設置し、広く
子どもたちの思いや考えを受け止め、市政運営の参考意見とします
いただいたご意見やご質問について、投稿された子どもや若者の
皆さんからの希望に応じて個別回答いたします
「こども・若者のご意見箱」は こちらから!
こちらから!
問い合わせ:環境保全推進課(電話:087-839-2393)
清潔で美しいまちづくりの主役は私たちです

・清掃用具を無料で貸し出しています
公共の場所などの清掃を行う場合に、清掃用具を
無料で貸し出しできます
貸出用具:ほうき、ちりとり、火ばさみ、熊手など
貸出期間:原則7日間以内
・ポイ捨ては絶対にやめましょう
ポイ捨てや不適切な処理をされたごみが海に流出して、
生態系への影響が心配されています
・犬のふんは必ず持ち帰りましょう
犬のふん放置禁止ポスターを希望者や自治会に配布
しています
・プラスチックごみを削減しよう
マイバッグやマイボトルなどを使って、使い捨てプラスチック
製品の使用を控えましょう
問い合わせ:保健所 生活衛生課(電話:087-839-2865)
殺処分ワーストからの脱却!たかまつwithわんにゃんプロジェクト
たくさんの犬や猫が殺処分されている現状を知っていますか?
保健所が市民から引き取ったり保護した犬や猫は、元の飼い主が
見つかれば飼い主へ返還され、見つからないか、いない場合は、
新しい飼い主へ譲渡されます
しかし、返還や譲渡されない犬や猫は殺処分になります
高松市は、犬や猫の収容数や殺処分数が多く、ともに全国でも
ワースト上位になっています
殺処分数を減らすために
犬猫一時保管施設(仮称)を整備します
収容した犬猫の十分な保管期間やスペースを確保するために、
犬猫一時保管施設(仮称)の建設(令和6年度 供用開始)を
予定しています
| 施設の役割 |
・引き取った犬猫の保管
・飼い主への返還
・健康管理 など |
犬猫の譲渡を推進します
さぬき動物愛護センター「しっぽの森」における
犬や猫の譲渡等事業を推進します
問い合わせ:障がい福祉課(電話:087-839-2333)
手話が伝わる、心がつながる
手話とは、手指の位置や動き、表情などを使った目で見る言語です
高松市では、「高松市手話言語及び障害のある人の
コミュニケーション手段に関する条例」を制定し、言語としての
手話に対する理解の増進や障がいの特性に応じた多様な
コミュニケーション手段の普及や利用の促進をしています
「高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケ-ション手段に関する条例」
高松市は、平成31年3月に高松市手話言語及び障害のある人の
コミュニケ-ション手段に関する条例」を制定しました
障がいのある人も障がいのない人も分け隔てられることなく、
お互いに人格と個性を尊重し合いながら、安心していきいきと
暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指しています
| 基本理念 |
言語としての
手話に対する
理解の増進 |
障がいの特性に
応じた多様な
コミュニケーション
手段の普及や
利用の促進 |

障がいのある人への配慮を考えてみませんか
「合理的配慮」を知っていますか?
「合理的配慮」とは、障がいのある人が、社会生活で生活しづらい
と感じる障壁を取り除く配慮のことです
まちの中にはたくさんの「合理的配慮」があるよ
私たちにできることを考えてみよう!
問い合わせ:生活衛生課(電話:087-839-2865)
人と動物が共に暮らせるまちづくりを目指して 近隣住民の迷惑にならないようペットは正しく飼いましょう
保健所には、犬や猫に関する多くの苦情や相談が日々寄せられています
動物を好きな人もいれば、苦手な人・嫌いな人もいます
人と動物が共に暮らせるまちづくりを実現するために、ルールやマナーを守って
飼いましょう
野良犬やの野良猫への無責任なエサやりはNG!
飼い犬が人をかんでしまったら保健所に届け出を!
不妊去勢手術を受けさせる!
飼い猫は完全室内飼いで!
犬の放し飼いは絶対にNG!
| 主な苦情・相談 |
・野良犬が怖い
・飼い犬を放し飼いにしている
・飼い犬の鳴き声がうるさい
・散歩の時に糞尿の処理をしない人がいる
・外飼いしている猫やエサやりで増えた野良猫が敷地内に糞尿をして困っている |
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
薬物乱用とは、医薬品を本来の用法・用量や目的をはずれて使用したり、
医療目的にない薬物を不正に使用したりすることです
薬物を不正に使用した場合は、たとえ1回使用しただけでも「乱用」です
薬物乱用の恐ろしさを理解し、薬物乱用を絶対に許さない社会環境をつくっていきましょう
覚せい剤、大麻、コカイン、指定薬物などの成分を含む危険ドラッグがあります
これらは所持しただけでも処罰されます
覚せい剤や大麻などの薬物に類似した化学物質を含む、極めて危険な薬物です
多くはハーブ、お香、アロマなどと目的を偽装して販売されていますが、
指定薬物や未知の危険な物質が含まれていることもあり大変危険です
吐き気、頭痛、精神への悪影響や意識障害などが起きる恐れがあります
摂取した人が死亡した例もあります
薬物乱用があなたの生活を壊します
薬物乱用により、意識を失う、呼吸困難などの身体への影響が生じるおそれがあり、
最悪の場合は死に至ることもあります
また、薬物による幻覚や妄想などで事件や事故など重大犯罪を引き起こすこともあります
薬物を何回も繰り返して使用したくなる依存性と、繰り返し薬物を使うことで
その効き目が薄れてしまう耐性が生じ、自分の意思では薬物の使用をコントロールできなくなります
誘惑に負けない、断る強さを!
薬物を乱用すると使用者の心身だけでなく、自身の将来を台無しにしてしまいます
甘い誘いがあっても、危険な薬物には決して関わらず、
誘惑されても「ダメ。ゼッタイ。」と断る勇気を持つことが大切です
その場のノリや好奇心に流されないようにしましょう
問い合わせ:環境総務課(電話:087-839-2388)
食べられるのに、捨てられる もったいないと思いませんか
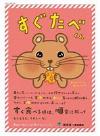
食品ロス削減をよびかける「すぐたべくん」ポスター
私たちにできる、食品ロス削減!
冷蔵庫の中を確認して、食材を買いすぎない
ようにしましょう
すぐ食べる食品は、賞味期限や消費期限の
長い商品を選択するのではなく、
陳列順に購入しましょう
食べ切れなかった食品は、冷凍などの傷みにくい保存方法を検討しましょう
また、保存した食べ残しを忘れないように、冷蔵庫の中の配置方法を工夫しましょう
問い合わせ:都市計画課(電話:087-839-2455)
50年後も暮しやすいまちを目指して
高松市では、人口減少においても持続可能なまちを目指して、
さまざまな施策・事業を実施しています
今回は、都市構造の集約化に向け、みんなが安全に安心して暮らすための
取り組みを紹介します
どうして集約化が必要なの?
昭和51年から平成26年にかけて、高松市では土地の開発が進み、
人口は平成27年まで増加していました
しかし、今後は人口の減少と高齢化などにより、まばらに居住地域が
分散され、都市機能が薄く拡がったまちが形成される恐れがあります
その場合、空き地や空き家が増える、公共交通の利用者が減少し
サービスが低下する、商店街などの利用者が減り、店舗の撤退・縮小
によりまちの活気が失われてしまうなど、持続可能なまちづくりを推進
するに当たり大きな問題となります
そこで、高松市では、次の2つの区域を設定しました
都市機能誘導区域 |
医療・福祉・商業などの都市機能を集約することで、
各種サービスを効率的に提供を図ろうとする区域 |
居住誘導区域 |
一定エリアで人口密度を維持し、生活サービスなどが
持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域 |
問い合わせ:男女共同参画・協働推進課(電話:087-839-2275)
LGBT誰もが自分らしく生きられる社会へ
「LGBT」という言葉を目にする機会が増えてきました
LGBTは性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)を表す総称の一つです
当事者の中には、差別や偏見などに苦しみながら生活をしている人もいます
誰もが自分らしく生きられる社会になるよう、LGBTについて正しく知るところ
から初めてみませんか?
| LGBT |
詳細 |
Lesbian (レズビアン) |
女性の同性愛者、女性の恋愛対象が女性 |
Gay (ゲイ) |
男性の同性愛者、男性の恋愛対象が男性 |
Bisexual (バイセクシュアル) |
両性愛者、恋愛対象となる人が女性と男性 |
| Transgender (トランスジェンダー) |
身体と心の性が一致していないため
身体の性に違和感を持ったり、
心の性と一致する性別で生きたいと望む人 |

![]() こちらから!
こちらから!