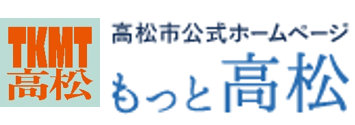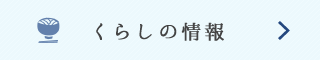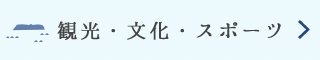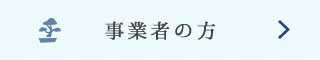高松さんぽ(令和6年度)
更新日:2025年4月2日
「勝手にシンドバッド」がやってくる(3月号掲載分)
「勝手にシンドバッド」。ご存知、国民的ロックバンド「サザンオールスターズ」(以下、サザン)のデビュー曲です。この歌を引っ提げて颯爽とサザンが登場してきたのは、私が大学に入学した1978年のことでした。リーダーの桑田佳祐(くわたけいすけ)さんが故志村けんさんのコントに着想を得て、当時はやっていた「勝手にしやがれ」と「渚のシンドバッド」を組み合わせて付けたという奇妙な曲名に、ビートの効いた底抜けに明るい曲調、意味深のようでよく分からない歌詞が、上京したてのうぶな大学生の頭に強烈な衝撃を与えました。そのサザンがついに、2月24日にオープンするサンポート高松の県立アリーナ(愛称:あなぶきアリーナ香川)に登場します。
残念ながら、私自身はチケットが入手できず、直接ライブを楽しむことはできませんが、大好きなバンドであるサザンが、1984年に高松市民会館で行われた公演以来、約40年ぶりに香川県内でのライブを行うことは、本当に嬉しいことです。個人的な感想で大袈裟に言えば、これだけでアリーナ建設の満足度効果の過半は満たされた気分です。
サンポート高松は、宇高連絡船の発着基地で四国の玄関口として栄えた高松駅周辺を香川県と高松市が連携して再開発したエリアです。そこに立地した県立アリーナは、県立施設ですが、高松市所有の底地の部分を県に無償貸付して、県市協調で新たなにぎわいの拠点として整備されたものです。
設計は建築界のノーベル賞と称されるプリツカー賞を受賞している金沢21世紀美術館などを設計した妹島和世(せじまかずよ)さんと西沢立衛(にしざわりゅうえ)さんによる建築家ユニットSANAA(サナア)の手によるもの。昔、NHKで放映されていた人形劇の舞台である「ひょっこりひょうたん島」を思わせるフォルムはユニークながら高松の港と瀬戸内海の風景に溶け込んでいます。オーストラリア・シドニーのオペラハウスに匹敵すると言っても過言ではなく、まさに世界都市・高松にふさわしい未来につなぐランドマークとなり得るものであると期待しています。
今年は巳年です。(2月号掲載分)
蛇ほど好き嫌いが極端に分かれる動物も珍しいのではないでしょうか。蛇を見ただけでも怖くて奇声を上げて逃げる人がいるかと思えば、ペットとして飼っている大蛇を首に巻きつけて喜んでいる人もテレビなどで見かけます。私ははっきりと、蛇は苦手なタイプに属します。蛇を見ると、一目散に逃げだしたくなります。
今年の干支は、「乙巳(きのとみ)」です。十二支の動物に当てはめると蛇。そこで、蛇にまつわる言い伝えや諺(ことわざ)を紹介しながら新年、令和7年が希望の年となるように願いたいと思います。
①蛇と金運
苦手な人の多い蛇ですが、巳年(みどし)生まれは「お金に困らない」と言われ、金運に恵まれる年だとも言われています。極端な円安や、不安定な国際情勢もあり、諸物価の高騰が続いていますが、言い伝え通り、国全体が金運上昇で経済が良くなってくれることを祈ります。
②竜頭蛇尾(りゅうとうだび)
竜のように頭は立派なのに、蛇のような細く貧弱な尾であるということから、初めの勢いは良いが終わりは振るわないことの例えとして使われています。今年は初心忘れずで、できれば「竜頭竜尾」といきたいものです。
③長蛇を逸す
大きなチャンスをあと一歩のところで取り逃がすという意味です。今年は、「大阪・関西万博」と「瀬戸内国祭芸術祭」が開催されます。高松が大いににぎわうであろうこの機会に、長蛇を逸することのない一年としたいものです。
④蛇に噛まれて朽縄(くちなわ)に怖(お)じる
「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」と同義の諺で、一度の失敗を過大に気にしすぎて、縄を見ても蛇と同じように怖がることを言います。失敗に反省は必要ですが、必要以上に萎縮すると、物事が悪い方向に後退しかねません。心したいものです。
⑤蛇足(だそく)
余計な付け足し、無用なものの意味です。昔、中国で蛇の絵を描く競争をした時に最初に書き上げた者が、つい足まで書いてしまって負けたという故事から来ています。
そこで蛇足ながら最後に私の好きな一行詩を添えておきます。
「蛇 ながすぎる」(フランスの詩人ルナールの「博物誌」より抜粋)
谷川俊太郎展など(1月号掲載分)
現代日本を代表する詩人の谷川俊太郎さんが昨年(令和6年)11月に亡くなられました。92歳でした。多くの日本人がそうであるように、私も大好きな詩人であり、その言葉の魔法に心踊らされっぱなしでした。特に、初めての詩集のタイトル「二十億光年の孤独」、という言葉はなんとも言えずカッコ良くて、よく口に出して使わせていただきました。作詞をされた「鉄腕アトム」のテレビアニメの主題歌も小さい頃よく口ずさんでいました。
その谷川俊太郎さんがさまざまな絵描きや写真家と作った絵本の展覧会が、昨年の7月20日から亡くなる2カ月ほど前の9月16日まで、高松市美術館で開催されていました。「谷川俊太郎 絵本★百貨展」と題されたもので、その作品を見てみると、最後まで絵と言葉による表現に果敢に挑んでおられた様子がよく分かりました。本市の美術館のホームページには、「バラエティ豊かな絵本に共通するのは、読み手に対する谷川俊太郎の希望の眼差しです」、と記してありました。そしてその眼差しの多くは、子どもたちに向けられていたように思います。今さら言っても詮無いことですが、感性豊かな谷川俊太郎さんの「言葉と表現」を一人でも多くの子どもたちにもっと味わわせてあげたかったと思います。
ご冥福を心からお祈り申し上げます。
ところで、高松市美術館の今年度の特別展の入場者が好調です。4月から始まった特別展「日本の巨大ロボット群像」は42日目に来場者数が一万人を達成。「谷川俊太郎 絵本★百貨展」は、開展32日目で一万人を達成しました。さらに、10月12日から行われた「五代浮世絵師展」は31日目で一万人を達成。しかも、外国人の来場が4・3%(令和6年11月30日現在)と多く、浮世絵の世界的人気がうかがい知れました。
「アニメ・ロボット」と「谷川俊太郎」と「浮世絵」。ある意味、日本を代表するテーマです。今年4月に始まる瀬戸内国際芸術祭を前にして、日本ならではの個性的な特別展の開催により、本市の芸術指数が少しずつ盛り上がってきているように感じられ、大変嬉しく思います。
扇の的・第二弾(12月号掲載分)
本市のシンボルである屋島は、平家物語で描かれる源平合戦の名場面、那須与一(なすのよいち)が活躍する「扇の的」の舞台です。その「扇の的」の故事を題材に、新作オペラが作られて、サンポートホール高松大ホールで上演されたのが、那須与一が扇の的を射てから830年ほど経った2014年でした。サンポートホール高松開館10周年事業として企画制作され、好評を博したこの「オペラ「扇の的」~ここからはじまる~」は、作曲、台本、出演者、演奏、広報などほとんどの分野で香川にゆかりのあるメンバーが参画、いわばオール香川で制作されたものです。そして、関係者のご尽力により、海外(ブルガリア)公演も行われました。
それから10年を経て、今度は、サンポートホール高松の開館20周年記念事業として、またしてもオール香川で、続編を制作する運びとなり、「「扇の的」~青葉の笛編~一ノ谷の合戦、屋島へ」が誕生、去る10月26日に世界初演が催されました。今回の舞台は、1185年2月の屋島の戦いの一年前、1184年2月の神戸、一ノ谷の合戦です。源義経(みなもとのよしつね)の鵯越(ひよどりこえ)の逆落(さかお)としで有名なこの合戦を題材として、そこで戦死した笛の名手、平敦盛(たいらのあつもり)とその妻、葵(あおい)の夫婦愛を描いた作品となっています。ちなみにこの物語のキー・アイテムである平敦盛が妻、葵に届けてくれと敵将、熊谷直実(くまがいなおざね)に託する青葉の笛は、空海が唐から持ち帰ったものだということです。ここにもこの物語の讃岐との結びつきがあります。青葉の笛を手にした葵は、夫、敦盛の戦死を悟り、この笛とお腹の中のわが子のために、ただ、生きるために生きようと決意し、船で屋島に向かうところでエンディングを迎えます。
新作オペラ「扇の的・第二弾」の完成により、古くから関西汽船やジャンボフェリーの航路で直接結びついていて、人や物の行き来も盛んな本市と神戸市との交流がさらに深まることを期待したいと思います。そして、海外も含め、多くのステージで再演の機会が得られることを願っています。
パラ陸上の聖地(11月号掲載分)
今年はオリンピックイヤーです。パリ2024オリンピック競技大会とパラリンピック競技大会が7月から9月にかけて催され、日本人選手の活躍などに日本中が大いに盛り上がりました。個人的に特に嬉しかったことは、高松市出身の日下尚選手がレスリング・グレコローマンスタイル77キログラム級で香川県出身選手としては初めてとなる個人種目での金メダルを獲得したこと。それにパラリンピックでは、日本人選手が14個という多くの金メダルを獲得したことです。特に、車いすラグビー、ゴールボールなどの人気種目での日本の金メダル獲得は、スポーツの持つ生きる力の後押しを実感し、感動を覚えました。
ところで、「パラリンピック」の語源をご存知でしょうか。元々は、両下肢麻痺者のリハビリテーションから始まったため、「Paraplegia(対麻痺者)」の「Olympic(オリンピック)」、あるいは、「Parallel(もう一つ)」の「Olympic(オリンピック)」という意味で名付けられたようです。そして、この「パラリンピック」という名称が使われ出したのが、1964年の東京オリンピックの時からで、日本発と言えなくもないのです。
そのパラリンピックにつながるパラスポーツの日本国内最高峰の競技大会と言われるジャパンパラ陸上競技大会が、9月28日(土曜日)と29日(日曜日)に本市の屋島レクザムフィールドで開催されました。3年ぶり2回目の開催です。屋島レクザムフィールドでは、2019年に日本パラ陸上競技選手権大会が、また、今年5月の神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会の日本代表選手の最終調整合宿が行われたことで、日本パラ陸上競技連盟の増田明美会長は、「高松は、パラ陸上の聖地と言っても過言ではありません。」とプログラムに記されています。
ただ、前回のジャパンパラ陸上競技大会は、コロナ禍の中、無観客で行わざるを得なかったことが、残念でした。それが今回は曇り空で暑さもそれほどでもなく、多くの観客にご来場いただき、間近でパラスポーツの魅力を感じていただけました。それが何より幸いであったと思っています。
玉藻よし讃岐国(10月号掲載分)
「玉藻よし讃岐の国は国柄(くにから)か見れども飽かぬ神柄(かむから)かここだ貴き…」
有名な飛鳥時代の歌人柿本人麻呂の讃岐国を歌った長歌の出だしの部分です。現代語に訳すると、「玉のような藻も美しい讃岐の国は、国の性格によるのか、見飽きないことだ。神の性格によるのか、たいへん貴いことだ」というもの。
この夏、さぬき高松まつりに並行して、夜型観光の振興の一環として「玉藻あかり物語」と銘打ったライトアップイベントを玉藻公園で開催をしました。そのプログラムの中に、高松市出身の女性能楽師、伶以野陽子(れいやーようこ)さんの天守台の石垣の上での仕舞(しまい)とライトアップされた桜御門前の舞台上での舞囃子(まいばやし)があり、それを鑑賞しながら「玉藻よし」で始まるこの歌を思い出していました。各演目は、いずれも地元ゆかりの「八島(やしま)」と「海士(あま)」です。
「八島」は言わずと知れた源平合戦屋島の戦いにまつわる話で、旅の僧が一夜の宿を借りた翁(義経の亡霊)から戦いの話を聞かされ、僧の夢の中にも出てきて合戦の様子が語られるものです。
「海士」は、お隣のさぬき市の志度寺を舞台とする話です。藤原不比等(ふひと)(淡海公)(たんかいこう)の妹君が唐帝の后(きさき)になったことから贈られた面向不背(めんこうふはい)の玉が龍宮に奪われ、それを取り返すために志度の浦に住んだ淡海公が海士と結ばれ一人の男子(房前)(ふささき)をもうけたこと、そして子を淡海公の世継ぎにするため、自らの命を投げ打って玉を取り返したことを語りつつ、玉取りの様子を真似て見せた海士は、ついに大臣房前に自分こそが母であると名乗り、涙のうちに海中に姿を消した云々、といった話です。
いずれも能や舞の世界では極めて著名な演目であり、このような演目が後世に伝わっていることが、人麻呂の歌った讃岐の国の国柄や神柄の良さを象徴的に示しているように思います。だから讃岐国の枕詞は、「玉藻よし」という美しくも雅なものなのでしょう。
余談ですが、アマモなどの海草や海藻は、二酸化炭素の吸収源としても期待されています。ゼロカーボンシティの実現に向けて「玉藻よし」の讃岐の貴重な資源を最大限活かしていきたいと思います。
地球沸騰化(9月号掲載分)
昨年7月、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は「地球沸騰化の時代が到来した」と警鐘を鳴らしました。世界平均気温が観測史上最高記録を大幅に更新したことで、これまでの「地球温暖化」という生ぬるい表現では伝えきれない危機的な状況に地球が差し掛かっているということを言いたかったのでしょう。そんな危機感がどんどん現実味を帯びてきています。今年の夏も、めちゃくちゃに暑かった昨年をさらに上回るような酷暑が続いています。
科学的には、東太平洋赤道地域の海面温度の高低による「エルニーニョ現象」や「ラニーニャ現象」が世界的な異常気象をもたらしているとのことです。地球温暖化に加え、特に今年は、「ラニーニャ現象」の影響で、日本付近では、夏季は太平洋高気圧が北に張り出しやすくなり、気温が高くなる傾向があるのだそうです。
高松でも、梅雨明けした7月の第三週から8月にかけて、連日最高気温が35度を超える猛暑日が続き、最低気温も軒並み25度を超え、熱帯夜の寝苦しい日が続きました。また、毎日のように四国4県に「熱中症警戒アラート」が発せられ、熱中症の疑いで救急搬送される人がずいぶん多くなっているようです。
地球温暖化の問題は、都市の持続可能性にも関わる問題で、思い切った政策転換が必要だと言われてきました。ごみ処理や交通、地域エネルギー、吸収源としての緑化や森林、農業政策など、脱炭素の取り組みは自分たちのまちづくり施策とも直結するのです。昨年7月に行われたG7香川・高松都市大臣会合でも、脱炭素を意味する「ネット・ゼロ」が主要議題としてトップに取り上げられています。
そのような中、7月下旬、本市と本市の指定金融機関である百十四銀行との間で、「脱炭素社会の実現に向けた連携協力に関する協定」を締結しました。地球温暖化に対処するための脱炭素の取り組みも、結局は、地域の企業や市民の意識改革と行動変容に関わってくるものです。それを促すための地道な活動を、関係者で協力しながら進めてまいりたいと思います。
ボンコラージュ(がんばれ)、ナオ!!(8月号掲載分)
7月26日(金曜日)に開幕したパリ2024オリンピック競技大会のレスリング日本代表に、本市出身の日下尚(くさかなお)選手が選出され、出場します。オリンピックでのレスリング日本代表選手に選ばれたのは香川県出身者では初の快挙です。
今回日下選手が出場するのは、グレコローマンスタイルの77キロ級。「グレコローマン」とは、フランス語で「ギリシャとローマの」と言う意味だそうです。変わった名前ですが、紀元前イタリア半島中部(今のローマあたり)にあった都市国家を形成していたエトルリア人の遺産とギリシャ式レスリングを元に復元され進化したのが原型で、アマチュアレスリングでは最も古い歴史のあるスタイルだそうです。フリースタイルと何が違うかというと、腰から下は攻撃してはいけないということ。全身の筋力がものをいいそうですね。
そんな日下選手を激励しようと、去る6月25日(火曜日)には、この4月に開設した高松市東京事務所のある丸の内のビルのイベントスペースで応援イベントが開催され、私からビデオレターで、「Bon Courage、NAO」(がんばれ、ナオ)とエールを送りました。日下選手は、6月9日(日曜日)にハンガリーで行われたランキング大会でも優勝し、このクラスで日本人初の世界ランキング・ポイント1位となるなど、本番を前に、オリンピックでのメダル獲得に向けて弾みをつけています。3年前の東京2020オリンピック競技大会では、本市出身でフェンシング・エペ団体に出場した宇山賢(さとる)選手が見事金メダルを獲得しました。日下選手もそれに続いて、高松市出身選手の連続金メダルも夢ではありません。
また、今回のパリ2024オリンピック競技大会には、日下選手に加えて、三木町出身でバスケットボール日本代表の渡邊雄太選手や坂出市出身で競泳200m平泳ぎの花車優選手も出場しています。現下の国際情勢は混沌(こんとん)として非常に不安定ではありますが、せめて、オリンピックというスポーツの祭典の最中は、嫌なことは忘れて、地元選手はもちろんのこと、日本代表選手を応援し、その活躍に何回も何回も快哉(かいさい)を叫びたいものです。
西のゴールデンルート(7月号掲載分)
インバウンド(訪日外国人)の多くが旅行する一連の日本の有名な観光地、東京、箱根、富士山、名古屋、京都、大阪などを巡る広域の観光周遊ルートのことをゴールデンルートと言います。初めて日本を訪れるインバウンド客であっても、日本を代表する観光都市をスポット的に気軽に体験できると人気があるのだそうです。主に、アジアからの観光客の周遊ルートとして使われることが多いようですが、アジア以外のヨーロッパやアメリカ、オーストラリアからのインバウンドを見ても、このゴールデンルート上にある都府県に滞在する人の数が飛び抜けて多いようです。
観光庁が取りまとめた2023年の統計では、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアから来たインバウンドのうち、ゴールデンルートにある6都府県(東京都、静岡県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府)の宿泊客数は全体の79.4%にもなるそうです。一方で、大阪府より西の、兵庫県、中国地方、四国地方、沖縄県を除く九州地方の西日本17県に宿泊した人は、全て足しても5.8%にしかならないということです。東京、大阪間のゴールデンルートとそれ以外の地域では、圧倒的に差がついているのが分かります。しかも、滞在日数が長く、高付加価値旅行者が多いと言われるヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアのインバウンドの滞在が西日本で極端に少ないことは、大きな経済効果を取り逃しています。
そこで設立されたのが「西のゴールデンルート・アライアンス」です。大阪・関西万博を前に、欧米豪の旅行者や高付加価値旅行者をメインターゲットに、産官それぞれの特徴を活かしながら一丸となって、万博などに訪れるインバウンドを大阪より西のエリアへ誘客しようというものです。去る5月17日に設立総会が行われ、提唱者の福岡市長が会長、神戸市長と広島県知事と私が副会長に就任することになりました。
設立総会時点で、47の自治体と多くの観光関連企業、団体も入った同盟組織。これまでにないスケールの大きな施策展開が期待されています。そして、その中心ルートとなるのは、九州と中国と四国をつなぐ瀬戸内海であると思っています。
5本の矢(アローズ)届かず(6月号掲載分)
スポーツにおいて、贔屓(ひいき)のチームを応援する人たちの呼び名は、プロ野球では、「阪神ファン」など普通に「ファン」ですが、サッカーでは、チームを支える「サポーター」と称されます。そして、バスケットボールでは、後押しする熱狂的なファンの意味で、「ブースター」と呼ばれます。特にプロバスケットボールの試合で、熱いブースターの存在と派手な声援、相手チームの攻撃に対する執拗(しつよう)なブーイングなどは試合を盛り上げる大きな要素でもあり、楽しみでもあります。
4月下旬に行われたプロバスケットボールB3リーグプレーオフ準決勝第2戦。延長戦までもつれた試合は、最後は、ブースターの歓声が悲鳴と大きなため息に変わり、香川ファイブアローズのシーズンは終了しました。残念ながら念願のB2リーグ復帰はなりませんでした。しかし、今年の香川ファイブアローズは、シーズンを通してリーグ戦2位の成績を残し、観客動員数も目標の一試合平均千五百人を超えるなど、来季につながる結果を残してくれました。
来季以降は、要件を満たせば現在建設中の香川県立アリーナがホームアリーナになる可能性があります。ちょうど、香川県が新たな県立体育館を整備する検討を行っていた時期に、プロバスケットボールのリーグを一本化した、Bリーグが創設され、サッカーJリーグの初代チェアマンでキャプテンの愛称で親しまれている川淵三郎さんが日本バスケットボール協会会長に就任。その際、B1リーグのチームライセンスとして観客席五千人以上のホーム会場を使用できることが条件とされました。
最終的に、サンポート高松地区の市有地の一部を無償貸付することとし、香川県がB1リーグの施設条件もクリアした上で、海に浮かぶ島のようなユニークな外観を持った、コンサート等もできる、新県立アリーナを整備することになったのです。
少し気が早いですが、いつかこの新県立アリーナにおいて、熱気あふれるブースターの声援の中、香川ファイブアローズがリーグ制覇を決める勇姿が見られることを今から楽しみにしています。
アートリンク10周年(5月号掲載分)
去る3月17日、瓦町フラッグにおいて「高松市障がい者アートリンク事業10周年記念トーク」が開催され、ゲストスピーカーとして参加してきました。
私が障がい者アートというものに初めて触れたのは、2009年に姉妹都市であるアメリカ合衆国フロリダ州のセント・ピーターズバーグ市を訪問した折でした。当時のリック・ベーカー市長が障がいを持った人々が熱心に芸術活動を行なっているので見てほしいと「クリエイティブ・クレイ」というNPO法人が運営する事業所に連れて行ってもらったのです。障がいのある人が自らの作品を誇らしげに掲げる、その生き生きとした笑顔に強い印象を受けました。芸術活動が障がいのある人の個性を引き出し、生きる力を与えているように感じました。
同じ頃、「クリエイティブ・クレイ」と交流がある岡山のNPO法人「ハートアートリンク」の田野代表理事が、アートリンク事業を高松でもやらないか、と提案してこられました。話はとんとん拍子ですすみ、2010年の瀬戸内国際芸術祭に併せて、アートリンクプロジェクトを開催し、高松の障がいのある高校生とフロリダのアーティストとがペアになり作った掛軸や、フロリダの障がいのある人と日本のアーティストがペアになり作った大きなウサギのバルーン作品などがサンポートに展示をされ、注目を浴びました。2013年の瀬戸内国際芸術祭にもアートリンクプロジェクトを行い、翌年からは、その発展形としてアートリンク事業を開始し、今回10周年を迎えることとなったのです。
令和5年度は、16か所の障害福祉サービス事業所等に11人のアーティストが派遣され、障がいのある人たちと美術、音楽、ダンス、陶芸、装飾等の創作活動をともに実施しました。また、姉妹都市60周年記念事業として、日米共作で「獅子」を3体作り、高松とフロリダ双方で創作的なダンスを披露し合いました。
田野さんは記念誌に、「各施設でのアートリンクで獲得した「まなざしの力」は、多様性を寛容に包括する力であると感じています」、と書かれています。障がいのある人の感性、創造性を育み、自分らしく暮らせる福祉社会の形成に資するものがアートリンク事業だと確信しています。
遍路道ウォーク~四国遍路を世界遺産に~(4月号掲載分)
去る2月23日の天皇誕生日、NPO法人「遍路とおもてなしのネットワーク」主催の「第9回一日一斉おもてなし遍路道ウォーク」に参加してきました。雨も小降りながら最後までやまず、あいにくの天候でしたが、八十三番札所一宮寺を出発して紙町、上之町を抜けて花園町観光通まで、約8キロ余りの行程を歩いてきました。同行していただいた関係者からお借りした菅笠(すげがさ)と和袈裟(わけさ)、金剛杖(こんごうづえ)で遍路衣装を整えると、不思議なことに雨もほとんど気にはならず、歩き終わると気分も清々しく心が洗われた思いがしました。これもご利益というものでしょうか。
高松市内5箇所を含む88箇所の札所を巡る四国遍路は、全長約1400キロにも及ぶ壮大な巡礼路です。歴史も深く、1200年を超えて継承されています。地域住民の温かい「お接待」を受けながら、供養や修行のため、救いや癒しなどを求めて弘法大師の足跡をたどる行脚は、自分と向き合う「心の旅」であり、世界でも類を見ない巡礼文化である、とされています。
「四国遍路を世界遺産に!」これが遍路道ウォークのスローガンです。参考としているのは、フランスとスペインをまたがる『サンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路』という、巡礼の道が世界遺産に登録された先例です。ここには、巡礼者に無料でワインと水を提供する「ワインの泉」や、格安の値段で泊まれる宿泊所「アルベルゲ」などがあるそうです。まるで、お遍路さんへのお接待と善根宿(ぜんこんやど)と呼ばれる簡易な宿泊所が今も残る四国遍路とそっくりではありませんか。
私がかつて島根県庁に在職していた時、江戸時代には世界の三分の一の銀を産出していたと言われる石見銀山跡を世界遺産に登録するために、ユネスコ本部などに調査に行ったことがあります。そこで多くの関係者から指摘されたのが、世界遺産は登録後にいかにその価値を良好な状態で保存活用できるかが大切であるということです。札所や遍路道をはじめ、関係施設の文化的価値を計画的に維持し、より高めていく努力が求められています。
お問い合わせ
このページは、秘書課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2131 ファクス:087-839-2129
(秘書係)
ファクス:087‐839ー2464(市長への提言)
<秘書課>
電話:087-839-2131
ファクス:087-839-2129