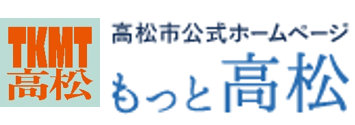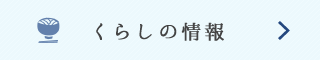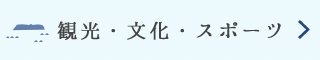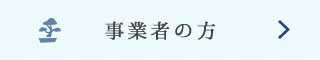第2回「株式会社フジPC屋島紡」
更新日:2024年11月14日
- 日時 7月30日(火曜日)午前10時00分から午後11時00分まで
- 会場 パワーシティ屋島店生活館3階
- 参加者 28名

今回、「パワーシティ屋島紡」の皆様方と、令和6年度第2回「市長まちかどトーク」を開催しました。
「パワーシティ屋島紡」は、複合施設の一角で、高齢者の生きがいづくりや健康寿命の延伸を目的とした、体操・音楽・文芸などの様々な講座を開催されており、地域の高齢者福祉及び介護予防に大いに御貢献いただいております。今回は、パワーシティ屋島紡の皆様と、「免許返納後の生活不安について」、「安全安心な公園を増やしてほしい」「災害時の避難・物資配給方法」などについて、意見交換が行われました。
【免許返納後の生活不安について】

身内の勧めと自己都合により免許を返納し、シニアカーを利用するようになり、初めて免許を返納した方の不便さを実感しました。
まず、シニアカーが通る道路は、舗装がされておらず穴も空いており、非常に危険であること。また、車道を通るなんてとんでもなく危険のため、家から外出することが減ったこと。公共バス・電車は駅が遠く、紡にも通う回数も減り、非常に認知機能が低下してしまいました。
どうか、行政とマルナカさんでもいいので、巡回バス等の代替になる乗り物をお願いいたします。
運転免許証の返納は、交通事故の加害者・被害者双方の防止につながる一つの手段であるが、公共交通機関がないと不便であることが一番の問題と認識している。
その代替手段として、いわゆるシニアカーを御利用される際、舗装が不十分な場所があるとのことで、本市では、市民からの直接の御連絡を始め、委託業者による修繕や維持管理のほか、昨年度からは市の公式LINEで市に通報できる仕組みを導入しているので、是非御利用いただきたい。
本市における公共交通は、ことでんとJRを合わせると、5つの電車路線、20以上のバス路線があるなど、40万人の人口規模の都市としては公共交通網が発達していると言える。一方で、利便性が高い「車」を使用し、公共交通に乗る機会が少ない市民が多く、このままでは公共交通の利用者が減り、利用者が減った路線は減便や廃線となり、その結果、より利用者が減る、といった悪循環を繰り返し、公共交通が衰退してしまうおそれがある。
そうならないため、本市では、鉄道を軸と考え、接続をよくするためのバス路線の再編や、電車やバスの乗継割引や高齢者向け半額割引のほか、地域主体によるコミュニティバスや乗合タクシーの補助制度を設けるなど、公共交通ネットワークの再構築に取り組んでいる。
路線バスやタクシーにおける運転手不足などの課題があるものの、これらの交通事業者への必要な支援を含め、引き続き、公共交通の確保・維持に取り組んでまいりたい。
【安全安心な公園を増やしてほしい】
毎日早朝と夕方に散歩をするのですが、昨今、安心してくつろげる公園が減少しております。
健康器具・運動器具・ベンチなどがあるとありがたいです。
また、万一災害が発生した際にも活用できる公園であれば、より安心できると思います。
シニアが立ち寄ることで子供たちの見守りになると思いますので、よろしくお願いいたします。
都市公園は、人々の休憩・休息の場、交流の場、レクリエーションの場のほか、美しい都市景観や防災活動の場としての役割があり、市民生活に欠かせない施設で、本市では、「1小学校区1公園」の整備方針に基づき、新たな公園を整備している。
公園整備の際には、遊具や休憩施設などの公園施設や、利用のルールづくりまで、ハード・ソフトの両方において、地元公園愛護会を始めとする地元関係者等の御意見・御要望をお伺いしながら進めている。
現在、スペース等の問題から新たな健康器具やベンチ等の設置は行っていないため、御相談いただければ、老朽化等に伴う既存遊具の更新の際に、種類の変更について検討したい。
また、公園は、災害時に重要な役割を果たす公共空間であり、規模の大きい公園を中心に指定緊急避難場所に指定している。今後、地域の実情を踏まえながら、公園の防災機能の強化についても検討してまいりたい。
【災害時の避難・物資配給方法】

昨今、異常気象など災害が全国に多発しているが、香川県は危機管理意識がとても低く感じます。
台風や洪水などの予測できる災害には対応ができるが、突然の地震などの予測ができないことが増えてきている。停電・水不足・支援物資が本当に必要になったとき、我々はどのような態勢をとればよいのか?
また、災害が少ない県のため、もっと他県にも役立つ県になるということも必要ではないでしょうか?我々市民も何かできることがないのかという御意見をいただきたいです。
「南海トラフ地震」の発生確率が高まる中、大規模災害が起きるたびに、「公助」の限界が明らかになる一方で、「自助」、「共助」の重要性が再認識されているところである。
災害時は、まずは「自らの命は自らで守る」意識を持ち、身の安全を確保した上で、「共助」による救助活動や安否確認のほか、避難所運営などの地域防災力の向上に取り組むことが、より重要となる。
また、停電や断水になった場合に、自宅で避難生活を送ることができるよう、自宅の耐震化はもとより、家具の転倒防止のほか、一週間程度の食料や飲料水、簡易トイレなどの備蓄品を備えていただきたい。
大規模災害発生時の被災地支援は、近年では、被災地の要望に基づいた支援が求められるようになっており、皆様方におかれましても、義援金や災害ボランティアなど、本市や日本赤十字社など公的機関からの要請に基づき、可能な範囲で御支援いただきたい。
本市では、住家の耐震化、家具の転倒防止対策及び一週間程度の備蓄の必要性について周知啓発を行っている。災害はいつ起こるか分からないので、改めて、常日頃からの十分な備えをお願いしたい。
お問い合わせ
このページは、広聴広報・シティプロモーション課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2161 ファクス:087-861-1559
(広聴係 本庁舎1階市民相談コーナー内)
電話:087-839-2111 ファクス:087-839-2464
<広聴広報・シティプロモーション課>
電話:087-839-2161
ファクス:087-861-1559