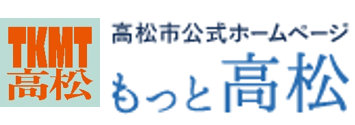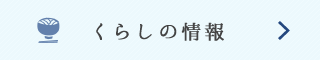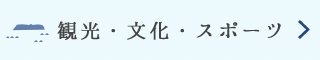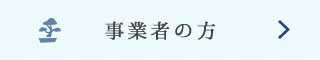高松市の水問題
更新日:2025年3月4日
節水型街づくり推進協議会 節水標語の入賞作品について
令和6年度節水標語優秀作品
<最優秀賞>
・「なんしょんな 出しよるその水 とめましょう!」 高松市立国分寺南部小学校 木曽 公輔さん
<優秀賞のうち2作を紹介します!>
・「ありがとう 水がくらしを ささえてる」 高松市立多肥小学校 池内 湧和さん
・「節水は みんなの問題 みんなの未来」 高松市立新番丁小学校 清水 あかりさん
(氏名の五十音順、学校名は受賞時のものです。)
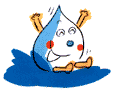
限りある水のこと。みんなで考えてみませんか?
雨の少ない高松市
本市の年間降水量の平年値※は1,150.1ミリメートルです。
これは観測データのある四国の県庁所在地の平均(約1,897ミリメートル)と比較して約6割であり、全国的にも雨が少ない地域と言われています。
※観測データの「平年値」とは、過去30年間のデータを平均した値のことです。
平年値は10年ごとに計算し、(現在は1991年から2020年までのデータ)2030年までは現在のデータを使用します。
乏しい高松市の水源
本市周辺には大きな川がないため、川の水を利用して貯水量の大きなダムを作るのは難しいのが現状です。
上水道用として使っている主な自己処理水源は、「内場ダム」と「御殿貯水池」などで、市全体の約56パーセントは吉野川(早明浦ダム)から導水した香川用水に依存しています。
香川用水(早明浦ダム)の水の危機
高松砂漠の再来と言われた平成6年の異常渇水では、厳しい節水生活を体験しました。
また、“四国の水がめ”早明浦ダムは、令和3年に2年ぶりの取水制限が行われました。
増え続けてきた水の使用量
生活様式の高度化、核家族化等の進行により、水の使用量は近年、増え続けてきました。
令和元年度の市全体の一人一日当たりの使用量は、300リットルで、昭和40年当時(162リットル)と比べて約2倍になっています。
平成6年の異常渇水以降、節水対策の取組み等により、水需要は横ばい状況にありますが、いざ渇水となると、現在の水道水源だけでは不足することが予測されます。
高松市の水問題対策のテ-マ 「渇水に強いまちづくり」をめざして
(1)水をつくる
ダムの建設
工業用水や農業用水の転用、下水処理水の河川への還流利用も検討課題としています。
ため池等の利用
ため池の整備、かさ上げなどを行い.貯水量をふやしたりしています。
水源の保全
ダム周辺の植樹の推進、水源地域の地下水の涵養や水源林の保全を促進しています。
海水の利用
海水の淡水化が研究されていますが、コストの点など引き続き調査検討がされています。
地下水の利用
学校、文化・スポ-ツ施設を中心に、順次、井戸の整備と利用を進めています。
(2)上水道の節約
節水をしよう
家庭や事業所で実践しています。
雨水の利用
本市では、公共施設での雨水利用を進めると同時に、市民・事業所などを対象に、雨水利用促進助成制度を設け、雨水利用の普及を推進しています。
再生水の利用
下水処理水の有効利用を図るため、平成6年度から下水処理水を浄化した再生水を供給しています。
(再生水供給量 最大1日あたり1,400トン)
令和3年4月1日現在、下水処理水循環モデル事業による施設を含め、JR高松駅など62施設に送水しています。
上手な節水方法
(家庭)
- 風呂の残り湯 再利用(簡易ポンプ等で)だとバケツ10杯の節水
- 食器洗い ため洗いでバケツ9杯の節水
- 洗車 汲み洗いだとバケツ21杯の節水
- 洗濯 ためすすぎだとバケツ5.5杯の節水
- 歯磨き コップに汲むと流しぱなしに比べコップ27杯の節水
- 雨水利用 雨水を散水、洗車などに利用
(事業所)
- トイレ 流水は1回だけに。擬音装置や節水型便器の設置
- 雨水利用 雨水を散水、トイレなどに利用
- 再生水の利用 汚水(雨水含む)等の再生水の循環利用
節水グッズの紹介
- 風呂水用ミニポンプ 風呂の残り湯を洗濯機等に。40~60リットルの節水
- 食器洗い機 流し洗いに比べ、50リットルの節水。時間も短縮。
- 節水型洗濯機 風呂水からの自動給水型、すすぎ方などの改良で節水できる洗濯機
- 追い焚き式風呂 追い焚きで再加熱。濾過装置とセットで効果さらにアップ
- 節水型便器 従来型は15~13リットル。節水型だと大8リットル小6リットルの使用量。
- 雨水貯留槽 屋根に降った雨水を溜めて使用。
- 風呂ブザ- 一定量になると、ブザ-の音が。入れ過ぎの心配はなし。
- 自閉式蛇口 一定時間が過ぎると自動的に水が止まる蛇口
- 泡沫式蛇口 蛇口から泡状の水が勢いよくでる蛇口
- 節水シャワ- 細かい目のシャワ-ヘッドを使用したシャワ-
- 節水コマ 蛇口に取り付けて流水量を少なくする部品
- 定流量弁 水圧に無関係で一定流量に制御するバルブ