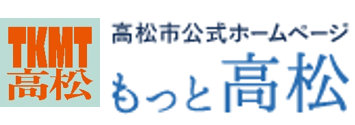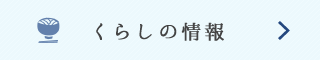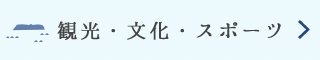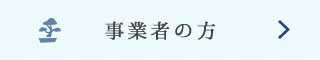人権全般
更新日:2018年3月1日
権教育・啓発図書一覧(人権全般)
| 分類番号 | 書籍番号 | 書名 | 著者 | 内容 | 出版社 | 発行年 | ページ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 人権のための教育 ー授業にすぐ使える活動事例集ー | ラルフ・ペットマン | オーストラリア人権委員会の編による、人権教育の教室向けの活動事例集。 | 明石書店 | 1984 | 235 |
| A | 2 | ポッカリ月が出ましたら | キョンナム | ”命さえ忘れなきゃ”清冽な感動と明るい哀しさの書き下ろしエッセイ。運転免許の更新が3年に一度なら、私の息災延命は1年ごとの更新。”命さえ忘れなきゃ”をキャッチ・フレーズに、大好きな晩秋から初冬にかけてのころ、新たな1年に向けて自分を励ますのが、もう二十年来の習慣となっている。そんな自分の周りの1年を、初冬の月から初めて、月とともに七つのとっておき話で綴る。 | 三五館 | 1992 | 221 |
| A | 3 | 新たな人権擁護制度を求めて | 高野 眞澄 | 元香川大学法学部教授が、日本社会における差別と人権の問題に焦点を当て、アイヌ、在日韓国・朝鮮人、障害者等被差別少数者に対する社会的差別についても必要な限り論及し、差別からの解放の抜本的な筋道を専攻分野である法(憲法)と教育の観点から解明している。 | 解放出版社 | 1996 | 281 |
| A | 4 | ことばのご馳走(4) -こころを癒す137の話 | 金平 敬之助 | 読んだ分だけ、元気になれる。うなずいた分だけ、穏やかになれる。家庭で、職場で、旅先で…。日常のさりげない言葉の優しさが、胸にしみ入る。 | 東洋経済 | 1997 | 212 |
| A | 5 | 当事者からみた日本の人権白書 | 人権フォーラム21 編 | 人権侵害された被害者・当事者から見た日本におけるさまざまな差別の実態と人権政策の課題について研究部会を開いた討論を参考にして各報告書でまとめた「当事者からみた人権施策の課題」を収録。 | 解放出版社 | 1998 | 303 |
| A | 6 | 人の値うち 江口いと人権の詩 | 江口 いと | 生活のなかで感じた被差別者の側に立つ苦悩と悲しみと憤りと願いなどを、決して背のびせずに、生活レベルで詠う詩集。 | 明石書店 | 1998 | 101 |
| A | 7 | 人権学習ブックレット(1) 人権とは? | 中川 喜代子 | 人間が人間らしく生きるために不可欠なもの”人権”。7つのアクティビィティ(参加型学習のフォーム)を家族、グループで体験する中で、たてまえではない人権感覚が身に付いていく。 | 明石書店 | 1998 | 51 |
| A | 8 | 世界人権宣言ってなに?第3版 | レア・レビン著プランチュ挿し絵 | 人権を保護するために、主要な人権文書とその実施手続き、及び国際組織の活動に関する情報を提供している。 | 解放出版社 | 1999 | 141 |
| A | 9 | ソーシャルスキル教育で子どもが変わる 小学校 楽しく身につく学級生活の基礎・基本 | 小林正幸・相川充 編 | ソーシャルスキル(人間関係に関する知識と具体的な技術やコツ)で友達づきあいのコツとルールを楽しく体験!思いやりのある子、楽しくふれあえる子、協力できる子を育てる。崩壊しない学級づくりに!! | 図書文化 | 1999 | 196 |
| A | 10 | エンカウンターで学級が変わる ショートエクササイズ集 | 林伸一・飯野哲朗ほか 編 | エンカウンターとは、ホンネとホンネの交流や感情交流ができるような親密な人間関係(体験)をいう。5分でできるエンカウンター。80個のショートエクササイズがギッシリ! | 図書文化 | 1999 | 213 |
| A | 11 | ワークショップは技より心 | (財)人権教育啓発推進センター | 最近の人権啓発活動や研修では、体験的参加型の手法として注目されているワークショップの準備するもの、下ごしらえ、手法ア・ラ・カルト等を紹介。 | (財)人権教育啓発推進センター | 2000 | 55 |
| A | 12 | 人権の視点で育てる総合学習 実践/プラン集 | 全国同和教育研究協議会 編 | 第49回、50回、51回の全国人権・同和教育研究大会の実践報告の中から総合的な学びを視野に入れてすすめられている活動をもとに編集。 | オフィスプロシード | 2000 | 149 |
| A | 13 | 多様性トレーニングガイド 人権啓発参加型学習の理論と実践 | 森田 ゆり | セクシャル・ハラスメント防止研修・簡易ディベート等43の参加型学習の実践方法を紹介。 | 解放出版社 | 2000 | 303 |
| A | 14 | 勇気がでてくる人権学習2 -差別・被差別・傍観のトライアングル〔人権ワークショップ〕 | 白井 俊一 | 体験参画型部落問題人権学習の入門書として好評を博した、前作の続刊。職場研修・地域懇談会用素材と、疑似体験ワークショップから人権意識への想像力が養われてゆく、さらに充実した1冊。 | 解放出版社 | 2000 | 156 |
| A | 15 | 人権教育への提案 -義理・人情から人権へー | ヒューライツ大阪 編 | アジア・太平洋地域の人権情報センターとして、事業をおこなってきたヒューライツ大阪が、人権の概念や国際人権と私たちの関わりなどの基本的な論点についてわかりやすく説明し、これまでの同和教育の取組み成果を生かしながら、今後の人権教育につなげていくための具体的なアプローチを提案する。 | 解放出版社 | 2001 | 101 |
| A | 16 | 緊急出版人権擁護法案・抜本修正への提案 | 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会 | 本当にパリ原則に基づいた実効性のある人権委員会を創設していける法案に修正し、差別や人権侵害に苦しんでいる当事者を真に救済できるものになるのか、人権擁護法案の問題点をつぶさに検討する。 | 解放出版社 | 2002 | 174 |
| A | 17 | 教師のためのアサーション | 園田雅代・中釜洋子・沢崎俊之編著 | 「自分の気持ちや考え、意見などを(相手に伝えたい場合は)、率直に、その場にあった適切な方法で述べる自己表現」、「自分も相手も大切にしたコミュニケーション」であるアサーション。小学校におけるアサーション・トレーニング『ドラえもん』のしずかちゃんになりアサーティブな表現を学ぶ等のトレーニング方法も紹介している。 | 金子書房 | 2002 | 197 |
| A | 18 | ひと味ちがう人権ワークショップ | 山中 千枝子 | 二十数年間、中学校教師をしていた著者が人権詩、子どもたちへのメッセージ、ひと味ちがうワークショップを綴る。 | 明石書店 | 2002 | 153 |
| A | 19 | 人権への教育と啓発 -囚われやこだわりの克服ー | 川嶌 順次郎 | 第1部では学生たちの回想、第2部では人権問題・同和問題の元凶とその克服、第3部では学校教育や社会教育、事業所や地域における最近の具体的な人権教育、人権学習の事例を紹介している。 | 東信堂 | 2002 | 200 |
| A | 20 | 人権のまちづくりガイドブック | 『人権のまちづくりガイドブック』編集委員会編 | 「人権のまちづくり」運動は、これまでの「部落のまちづくり」と異なり、その舞台を周辺地域(コミュニティ)にまで広げるものである。また、現代社会がかかえるさまざまな困難の解決と、市民一人ひとりの自立や自己実現への見取り図を、地域というキャンバスに、市民協働の力で描いていこうというチャレンジでもある。 | 解放出版社 | 2003 | 95 |
| A | 21 | 涙が出るほどいい話 第八集 | 「小さな親切」運動本部編 | 1985年の「第1回『小さな親切』はがきキャンペーン」から2002年の第18回までに応募のあった、およそ84、000通のはがきのなかから117篇を収蔵。日本中を感動の渦に巻き込んでいま1000粒の涙が光る。ジワっと心にしみてまた人が好きになる。 | 河出書房新社 | 2003 | 189 |
| A | 22 | 辛淑玉のアングル | 辛淑玉 | 私は、つらい体験を声にした。声にしたからこそ、それに応えてくれる人がいた。理不尽さと向き合う勇気を、人と人とのあたたかな関係をつくる醍醐味を、「見えない差別」をキャッチした在日の視線で綴る。 | 草土文化 | 2003 | 137 |
| A | 23 | ヒューマンライツは複数形「ジャーナリストの直視斜眼」 | 稲積 謙次郎 | 「人権のバブル化現象」を撃つ。ジャーナリストの鋭い視点。人権の世紀に、いま、どう向き合うか。タブーに挑戦し続けた体験を重ね合わせながら綴った渾身のレポートに、その答えがみつかるはずだ。 | 西日本新聞社 | 2003 | 328 |
| A | 24 | 鏡は先に笑いません | 金平 敬之助 | ひと言のやさしさで人は救われ、ひと言の温もりから明日の勇気が生まれる。 | 東洋経済 | 2003 | 210 |
| A | 25 | キム先生の人権のおはなし ー感性にひびく48章ー | 金 両基 | 静岡県磐田市の「広報いわた」に平成6年6月号から平成11年3月号までの5年間掲載された「人権コラム」のうちから42編を採録し、あらたに書き下ろし6編を加えた外国人の筆者が書く人権コラム。 | 明石書店 |
2003 | 111 |
| A | 26 | 保健室のクッキー (児童書) | 上條さなえ・作 相澤るつ子・絵 | ぼくはクッキー。つよーいチワワなんだ。ママや弟のミロと動物病院でくらしていたけれど、院長先生に「わるい子!」っていわれて、「しゅぎょう」に出されちゃった。ぼくの「しゅぎょう」は、小学校の保健室でおしごとすることなんだって…。弱虫のクッキーは保健室の仕事や冒険をとおして、弱くてもいい、みんな違っていいと思う。 | 汐文社 | 2003 | 99 |
| A | 27 | 大切なこと | 松下幸之助・文 江村信一・絵 | あたり前だと思うことこそに目を向けてみよう。そこにはきっとしあわせがある。月刊誌『PHP』の裏表紙にこれまで連載してきた短文をまとめた書籍。 | PHP研究所 | 2003 | 95 |
| A | 28 | 人権読本 じんけんの詩Ⅲ | 今野敏彦・編著 福永由美子・さし絵 | 知識より感性に訴え、大きく感動をよび起こす人権教育の教材となるじんけんの詩集。 | 明石書店 | 2003 | 64 |
| A | 29 | 人権と仲間関係2004 子どもが光り輝く時 パートⅡ -人権行動の育ちー | 人権と仲間関係研究会 | 人権と仲間関係研究会が人権保育の実践報告をまとめ報告している。 | 解放出版社 | 2004 | 106 |
| A | 30 | 人権教育美郷からの発信 -人権教育だより『ほたる』の営みを通してー | 美郷村教育委員会 | 徳島県美郷村がが発行した人権教育だよりを掲載。 | 美郷村教育委員会 | 2004 | 205 |
| A | 31 | 人権教育を生かした学級づくり かず先生のメルマガ通信 | 松下 一世 | 小学校の先生である著者が、週一回発行したメールマガジンをまとめたものである。多くの子どもたちの事例を紹介しつつ、カウンセリング理論や教育心理学を取り入れながら、子どもたちの気持ちや行動を分析し、子どもたち自身が豊かな人間関係作りの力をつけていくための道すじを模索している。 | 明治図書 | 2005 | 146 |
| A | 32 | 人権相談テキストブック | 北口末広・村井茂 編 | (財)大阪府人権協会が人権相談推進事業(人材養成・育成事業)としておこなっているこの講座の内容をもとに編集したものです。 | 解放出版社 | 2005 | 435 |
| A | 33 | とっておきの道徳授業Ⅳ「あい」で創る35の道徳授業 | 佐藤 幸司 編著 | つらい事件が多発している、今、強く求められている道徳の授業。自分自身を大切にし、命あるすべてのものを愛せる心を育てる授業35選を収録!今だからこそ子どもたちに届けたい。あいのメッセージ! | 日本基準 | 2005 | 159 |
| A | 34 | 中学校編 とっておきの道徳授業Ⅲ 6つの願いで創る35の道徳授業 命・正義・悩み・生き方・社会・そして愛 | 桃崎 剛寿 編著 | 「この時代を生きる中学生に」教師の願いをこめた35本のオリジナル道徳授業。「素材を生かすための工夫」「授業展開の工夫」を展示!オリジナルの道徳授業を創り出すヒントになる。 | 日本基準 | 2005 | 159 |
| A | 35 | 人やまちが元気になるファシリテーター入門講座 | ちょん せいこ | ファシリテーションは一人ひとりがもつ知恵や力を上手に引き出し、融合する。合意形成や課題解決の知恵を上手につくる、とても優れたツール(道具)なのです。学びや会議の場、そこに育まれる人間関係をとても豊かなものにしてくれる。 | 解放出版社 | 2007 | 147 |
| A | 36 | 私の人権行政論 ーソーシャルインクルージョンの確立に向けてー | 炭谷 茂 | 2006年11月から「国際人権大学院大学の実現をめざす大阪府民会議」主催のプレ国際人権大学院大学講座でした10回の人権講義を記録した。 | 解放出版社 | 2007 | 205 |
| A | 37 | 人権の絵本(1) じぶんを大切に | 岩川直樹/文 木原千春/絵 | 人権を尊重する人間と社会。その土台には、じぶんを大切にするということがどうしても必要になる。じぶんを大切にするとは、なにをどうすることなのかを問いつづけながらつくられた絵本。 | 大月書店 | 2000 | 36 |
| A | 38 | 人権の絵本(2) ちがいを豊かさに | 岩川直樹/文 木原千春/絵 | 人権を尊重するために、暮らしのなかで出会うさまざまなちがいを豊かさにしていく道を探る。 | 大月書店 | 2000 | 36 |
| A | 39 | 人権の絵本(3) それって人権? | 喜多明人/文 木原千春/絵 | 人間として生きていくためにとても大切な「人権」とどう出会うか、ふだんの生活で「なにかおかしいな」と感じるようなできごとのなかから、“人権を感じとる”ことの大切さを考える。 | 大月書店 | 2000 | 36 |
| A | 40 | 差別用語の基礎知識’99 | 高木正幸 | 差別語・差別表現として団体等から抗議、糾弾を受けたり、事前に言い換えや、削除された事例200余りを分野別に取りあげ、今後の対策を詳しく解説。 | 土曜美術社出版販売 | 1999 | 392 |
| A | 41 | 人権の絵本(4) わたしたちの人権宣言 | 喜多明人/文 木原千春/絵 | 私って何?人権って何?を考える。生い立ちのちがうケンタ、リエ、ジョーの3人が成長とともに人権を学び、主張していく。 | 大月書店 | 2000 | 36 |
| A | 42 | 人権の絵本(5) タイムトラベル人権号 | 満川尚美/文 木原千春/絵 | 私って何?人権って何?を考える。教室で、サークルで、討論しながら学べる絵本。タイムマシンに乗って、世界と日本の人権の旅へ出発! | 大月書店 | 2000 | 38 |
| A | 43 | 人権の絵本(6) 学びの手引き | 岩辺泰吏/編 | 私って何?人権って何?を考える。いじめで苦しんだり、じぶんを見失って悩んでいる子どもたちが、じぶんを見つめ、お互いを信頼しあえるために。資料・用語解説から授業実践まで、調べ学習と活用のための手引き。 | 大月書店 | 2000 | 74 |
| A | 44 | 屠場文化 -語られなかった世界- | 桜井厚/編 岸衛/編 | そこにありながら見ることを避けてきた”屠場”。そのローカルな文化の全体像を人びとの濃密な「語り」から描きだす。 | 創土社 | 2001 | 254 |
| A | 45 | 別冊スティグマ 人権教育ブックレット(1) なぜ今、人権教育が必要なのか? | 福田弘 | 人権教育の指導方法の基本原理を踏まえた上で、人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成にどう取り組むべきかについて、具体的に考察する。 | 千葉県人権啓発センター | 2008 | 136 |
| A | 46 | 改訂版 実例・差別表現 あらゆる情報発信者のためのケーススタディ | 堀田貢得 | 部落問題、障害者問題、民族問題など、マスメディアでおきたあらゆる事例をもとに、糾弾された理由からその後の対応までを詳細に紹介する。 | ソフトバンククリエイティブ | 2008 | 383 |
| A | 47 | 差別からみる日本の歴史 | ひろたまさき | 差別とは?差別の構造とは?原始・古代から現代までの差別を論じた意欲作。 | 解放出版社 | 2008 | 413 |
| A | 48 | 人権ポケットエッセイ 1 | 大阪府人権協会/編 | 「人権」にかかわって活躍している人たちの、日ごろの活動や思いを、等身大で紹介するエッセイ集。部落問題や女性問題、障がい者問題、高齢者問題、外国人問題、ハンセン病問題、子どもの人権問題などさまざまな人権問題にかかわってきた人たちの姿を伝えている。 | 大阪府人権協会 | 2008 | 109 |
| A | 49 | 人権学習シリーズ 暮らしのなかの人権 | 鳥取県人権文化センター/編著 | 身近な暮らしのなかから人権とは何かを学ぶ体験型学習・研修の入門書。 | 解放出版社 | 2008 | 84 |
| A | 50 | 広告と人権 | 宗像勝年 | 人権問題を理解しないで広告表現に携わることは、交通法規を無視して車を運転するようなもの。多くの事例から読み解く、担当者必見の人権問題指南書。 | 文芸社 | 2009 | 221 |
| A | 51 | アイスブレイク入門 こころをほぐす出会いのレッスン | 今村 光章 | 見知らぬ人どうしの出会いを演出する技術。世の中の出会いを豊かにするアイスブレイクについての入門書。 | 解放出版社 | 2009 | 94 |
| A | 52 | 子どもの人権力を育てる -尊敬を軸にした人権保育 | 玉置 哲淳 | 乳幼児への尊敬の問題を提起し、大人が乳幼児への年齢的偏見があることを議論する必要性を述べ、保育を考えるきっかけとなる書。 | 解放出版社 | 2009 | 158 |
| A | 53 | 「ホームレス」襲撃事件と子どもたち いじめの連鎖を断つために | 北村 年子 | がんばれない自分、うまくやれない自分。その最大「最低」の象徴として、子どもたちは「ホームレス」の人びとの姿を嫌悪し、憎悪する。野宿者襲撃は、学校でのいじめの延長線上にある。 | 太郎次郎社エディタス | 2009 | 429 |
| A | 54 | 元気のもとはつながる仲間 -解放教育の再生をめざして- | 外川 正明 | 各地で「部落問題の解決を自らの生き方の課題」として地道な実践を積み上げている「仲間たちの姿」を紹介する。 | 解放出版社 | 2009 | 268 |
| A | 55 | 北の風 南の風 部落、アイヌ、沖縄。そして反差別 | 竹内 渉 | 被差別部落出身でアイヌ「社会」内部に暮らし、アイヌ・沖縄・被差別部落の交流の橋渡しをしてきた著者による反差別について書かれた書。 | 解放出版社 | 2009 | 231 |
| A | 56 | 無縁社会 〝無縁死〟三万二千人の衝撃 | NHK「無縁社会プロジェクト」取材班/編著 | 地縁、社縁、血縁が崩壊し、身寄りのない無縁死が急増している。「無縁死」した人々やひとりきりで生きる人々の人生を取材した記録から無縁社会について考える。 | 文藝春秋 | 2010 | 269 |
| A | 57 | 人はひとりで死ぬ 「無縁社会」を生きるために | 島田 裕巳 | 世のあらゆる縁を失い、孤独な死を迎える-「無縁死」することへの不安がいま広がっている。この無縁社会のなかで、ひとりひとりが十分に生き、そして死んでいくために見すえるべき真実とは何か。 | NHK出版 | 2011 | 215 |