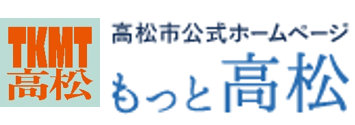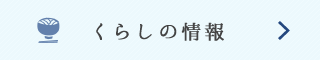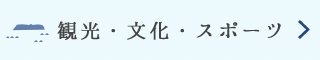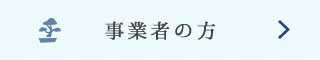令和3年7月
更新日:2021年7月7日
教育長ひと言
教育長が、教育に関する想いを「この月に想う」と題して綴ったコラムです。
「七月に想う」 ♪輝く星に 心の夢を 祈ればいつか叶うでしょう

7月7日は「七夕」です。織姫と彦星が、一年に一度だけ、天の川を渡って逢える日です。織姫は織女星と呼ばれ、理科の授業では、こと座の1等星「ベガ」と学習します。青白く輝く星で、全天で4番目に明るい星です。彦星は牽牛星と呼ばれ、わし座の1等星「アルタイル」と学習します。どちらも同じ1等星ですが、アルタイルはベガよりもやや暗く、色も少し黄みをおびています。そして、その間にあり、太陽のように自ら光り輝いている恒星が、およそ2,000億個も集まっているミルキーウェイとも呼ばれる天の川、私たちの銀河系です。理科の教師として、この程度の知識は持っていたのですが、ふと、七夕の伝説と、短冊に願い事を書いて笹竹に飾るのは、どういう関係があるのだろうという疑問を持ちました。そう考えていると、「七」に「夕」と書いて「たなばた」と読むのはどうしてだろう、織姫と彦星は、確か夫婦であったはずなのに、なぜ一年に一度だけしか逢えないのだろう、いつからこのような風習があるのだろうなどと不思議なこと、分からないことがどんどん出てきました。
これらの疑問を調べてみると、たった5画の言葉である「七夕」の由来には、大変奥深いものがあり、根付いた風習は、形を変えながら現在まで引き継がれてきていることに驚きさえ感じました。その過程で、子どもの頃によく飲んだカルピスが1919年7月7日の発売であり、それに因んで、パッケージに天の川の星々を水玉模様に表したということも知り、なるほどと合点した次第であります。
「七夕」の願い事が、絵本のタイトルになっているのが、くすのきしげのりさん・作、石井聖岳さん・絵の「おこだでませんように」です。読んだ方もたくさんいらっしゃることだと思いますが、私は、10年ほど前の校長時代に、この絵本を、若い教員に少年役をお願いし、私とともに、職員に読み聞かせをしました。子ども向けの絵本かもしれませんが、大人にも読んで欲しい、特に子どもに向き合う教師には是非とも読んで欲しい絵本だと思い、読み聞かせをしたのです。
学校でも、家でも、叱られてばかりいる少年が、口答えもせずに、胸の中で語る言葉に、私にも、絵本の中の先生やお母さんのように振舞った心当たりがあり、身につまされるのです。「あーあ、ぼくは いつも おこられているばかりや」とつぶやく彼が、学校で七夕の笹竹につるす短冊に願い事として書いたのが、タイトルの「おこだでませんように」です。一番の願い事を一生懸命に考えていると、「はよう書きなさい。」と、また叱られて、一文字ずつ、たどたどしい字で、間違った表現もありますが、教えてもらったひらがなに心を込めて書いた願い事が、「おこだでませんように」となったのです。その短冊を読んだ先生は、彼の心を慮って、・・・。
この絵本は、大切なことを私たち大人に伝えてくれます。もちろん、子どもに接する際の大人として振る舞いもそうでしょう。さらに、子どもたちが書いた願い事や、その子の言動には、多くの様々な背景があることに気付かなければならないと思いました。単に、この子は、こんな願い事をしているのかと知るだけではなく、その背景にあるもの、その意図することに目を向ける周囲の大人の心が、子どもの祈りのような願いを叶えることになるのではないでしょうか。
長引くコロナ禍の中、子どもも大人も慎ましく生きながら、希望を見出だそうと懸命に生きています。「星に願いを」届けられますように。
きたい。