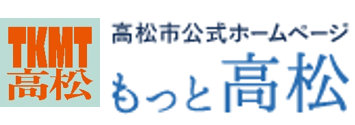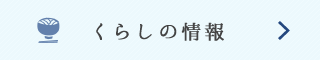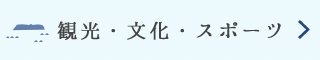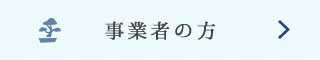令和元年8月
更新日:2018年3月1日
教育長ひと言
教育長が、教育に関する想いを「この月に想う」と題して綴ったコラムです。
「八月に想う」今こそ振り返りたい「二十四の瞳」の教え

先日、壷井栄さんの小説「二十四の瞳」の舞台になった小豆島の「岬の分教場」を訪れた。とはいえ、都合で「二十四の瞳映画村」にある「岬の分教場」になってしまったが、そこで、大学時代のサークル仲間の壷井栄文学館大石雅章館長が演じる「二十四の瞳」の紙芝居を小さな椅子に座って見た。
この原作が木下恵介監督によって映画化され、大石先生を高峰秀子さんが演じた映画を観た記憶がある。モノクロだが、大変美しい日本の風景、先生と子どもたちの温かくせつないやりとり、そして、貧しさと時代が子どもたちを翻弄していく中、ただ思い願うことしかできなかった不条理さなどが、本を読んだ時と同様に強く印象に残った。
小石先生、なきみそ先生と子どもたちに言われながらも慕われた大石先生だが、学校を舞台にした他の物語やドラマのように、子どもたちの胸を打つような名言を先生が言うことはない。ただ、子どもたちとの会話の一つ一つが、子どもたちの暮らしぶりや心情を丁寧にくみ取り、その気持ちに寄り添うように語られる。
物語の中盤、大石先生は、女の子たちの進路を心配している。先生になりたくて師範までいきたいという子どももいれば、家の事情で、6年で学校をやめるという子どももいる。コトエもその一人だった。母親が父と漁に出ていて、女である自分は、家で飯炊きをしなければならない。算数はいつも満点のコトエだが、男の子に生まれなかったことに肩身の狭い思いをしているコトエであった。コトエが決めた進路を聞いた時に「それはまちがっています。」と言いかけて、コトエが運命を受け入れようとしている覚悟にその言葉を飲み込み、かける言葉を探す。そして、一言、「残念ですね。」と言う場面がある。
子どもは、大人がかけてくれる言葉を、自分のことを思って言ってくれているのか、それともうわべだけの言葉なのか、瞬時にかぎ分ける能力を持っている。コトエは、大石先生のその一言で気持ちが軽くなり、現実を受け入れ、前を向く自分を語り始める。私たちは、子どもたちのそのような能力に応えるだけの心のこもった、理解ある言葉をかける深い関わりと愛情を持っているだろうか。けっしてハッピーエンドとは言えない物語であるが、子どもを教え導くなど大それたことはできなくとも、変わらぬ深い愛情を持ち続け、子どもの気持ちに寄り添うことならできると「二十四の瞳」は教えてくれる。
私は、平成6年の春からの3年間を、「岬の分教場(田浦分校)」の本校にあたる内海町(現:小豆島町)立苗羽小学校で教頭として勤めた。とても懐かしく、私の教師生活の中で、一輪の花のように愛しい時代である。担当した地区児童会は分教場がある堀越・田浦地区であり、行事等があるたびにでかけ、分教場に入り、訪れる人が綴ったノートに目を通した。多くの人が、様々な思いを綴っていた。中には、椅子に座って数時間を過ごす人もいたということを聞いた。
「岬の分教場」は、「二十四の瞳」によって教育の原点と言われているが、すべての人に本を読み、一度は訪ねてもらいたい場所である。