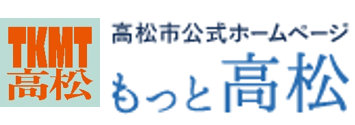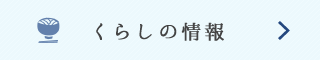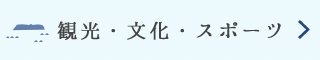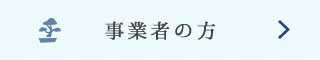令和6年6月
更新日:2024年7月19日
「六月に想う」 子どもの学びをつなぐ

5月から6月にかけては、バラの花が美しく咲き誇る季節です。甘い香りに誘われてミツバチや虫たちもたくさん飛び交います。この時期、こども園や幼稚園を訪問すると、園児たちが楽しそうにパンジーの花壇の中のツマグロヒョウモンの幼虫を集めている姿を見かけます。この幼虫、見た目はグロテスクで毒々しい色合いですが、実はとってもきれいな蝶に羽化することを、園長先生から教えていただきました。
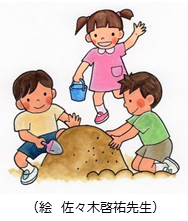
「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」という言葉があります。もともとこの言葉は、“All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten”という、アメリカのロバート・フルガム氏が書いた本のタイトルですが、幼児教育についてうまく表現した言葉だと感心します。
何でもみんなと分け合うこと、ずるをしないこと、使ったものを必ず元のところに戻すこと、誰かを傷つけたらごめんなさいと言うことなど、大人から見ると、ただの遊びだと思う中で、子どもたちは、実に人生において大切な事を学んでいることに気付かされます。
さて、5月から学校訪問が始まるとともに、小学校の校長先生とお話をする機会が多くありました。多くの方々から、「今年はこれまで以上に、小学校に入学してきた1年生が、生き生きと落ち着いて学校生活を送っています。」という言葉をお聞きしました。幼稚園、こども園、保育所から小学校に入学してくる1年生は、生活や環境の大きな変化の中で、かなりのストレスを抱えることになりますが、自分なりに居場所を見つけて、楽しく学校生活を送っている様子をお聞きし、何よりうれしい気持ちになりました。
高松市では、令和4年度から文部科学省の研究指定を受け、「幼保小の架け橋プログラム」に取り組んでいます。市内のいくつかのモデル校区を中心に、就学前施設と小学校の教職員がお互いの理解を深めながら教育を進めています。
モデル校区では、小学校の入学式に参加した1年生が、「校長先生!」と言って小さく手を振る姿や、来賓席のこども園の先生に笑顔を返す姿が見受けられます。また、1年生の担任の先生が接続を意識したカリキュラムを工夫し、何を教えるかより、子どもがどう学ぶかに視点を移し授業等を進めるようにしているなど、徐々に成果が見えてきています。
さて、小・中学校間の接続についてはどうでしょう。中学校区によっては、小学生が中学校生活の一日体験をしたり、小・中学生が一緒に朝のあいさつ運動や文化祭を実施したりしています。また、教職員がお互いの授業を参観し合ったり、校区内の小・中学校の若年教員が定期的に集まって自主合同研修を実施したりと、よく言われる中1ギャップの解消に努めている学校が多くあります。
昨年度からのコミュニティ・スクールの取組により、学校運営協議会を中心に、地域とともにある学校づくりが市内全体で進んでおり、家庭や地域との横の連携が充実してきました。それらに加え、就学前施設、小学校、中学校間を見据え、縦の連携・接続を意識した取組を進め、子どもたちへの熱い思いを持った先生方が互いに子どもの姿を伝え合い、気軽に対話を重ねることにより、子どもの学びがつながっていくことを願っています。