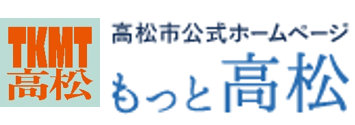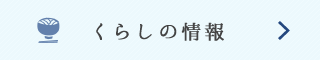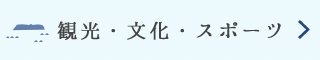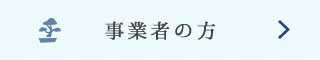第4章 施策の展開 4
更新日:2021年3月22日
4 生活・就労支援の推進
障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、障がい者の様々なニーズに対応する障害福祉サービス等の質・量の充実を図り、障がい者が生活に必要なサービスを自由に選べるようにしていくことが重要となります。介護者の高齢化対応や介護疲れからの虐待防止の観点から、家族介護者の負担の軽減も必要となっています。
障がい者の社会参加や経済的自立において、就労は重要な役割を担うことから、福祉・教育・労働関係機関等と連携し、法定雇用率の遵守等、雇用促進に向けて企業等へ積極的な啓発を行うとともに、企業等における障がい理解の促進や支援の充実を通じ、雇用の場の拡大を推進します。
また、就労支援サービスの充実や、一般就労が困難な人の働く場として福祉的就労の基盤の充実を図り、様々な状況の障がい者が働くことのできる環境の整備に取り組みます。
さらに、令和2年3月に策定した「高松市障がい者活躍推進計画」に基づき、本市における障がい者雇用と障がい者である職員の活躍の推進に取り組みます。
| 事業内容 | 目標項目・ 見込項目 |
令和元年度 実績 |
令和5年度 目標・見込量 |
|---|---|---|---|
| 市役所内障がい者就労の場の開設 | 参加者数 |
434人 | 500人 |
| 中央商店街の空き店舗を活用した障がい者雇用への助成 | 助成事業者数 | 1事業者 | 2事業者 |
| 本市における障がい者の職員採用 | 障がい者雇用率 |
2.03% |
2.6%以上 |
(1)障害福祉サービス等の充実
【現状と課題】
障がい者一人一人の多様なニーズに対応し、障がい者が豊かな地域生活を実現させるためには、利用者が自らの選択により、適切に利用できるサービスの量的・質的な充実や生活支援体制の整備等、サービス提供体制の充実を図る必要があります。アンケートやグループインタビューからも、障害福祉サービスについて多様なニーズがあることが分かります。
「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」に基づき、障害福祉サービス等の充実を図るとともに、障害福祉サービス等の分かりやすい情報提供に取り組みます。
また、親亡き後の生活を心配する声も聞かれることから、重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の地域での自立生活を支援するとともに、施設等からの地域生活への移行における住まいの場として、グループホームの充実等を図る必要があります。
【具体的取組】
- 障がい者が利用できるサービスを適切に選択できるようにするため、広報紙やホームページ等を通じて、障害福祉サービス等の情報を適切に提供します。
- 基幹相談支援センター・相談支援事業所等と緊密に連携し、障がい者に、障害福祉サービス等のサービス内容や、サービス提供事業者等の情報を、分かりやすく、適切に提供します。
- サービスの質の向上を図るため、サービス提供事業者・人材の確保、育成等を支援します。
- 日常生活用具給付事業等地域生活支援事業について、障がい者のニーズを踏まえ、サービス内容の充実を図ります。
- 個々の事業者の質の向上を図るとともに、利用者が適切なサービスを選択できるようにするため、事業者の提供する福祉サービスの質を公正・中立な第三者評価機関が評価する、福祉サービス第三者評価の受審を促進します。
- 利用者の生活の質的向上を図るため、社会福祉施設における利用者等の苦情解決に努める苦情解決制度の普及を促進します。
- 地域共生社会の実現に向けた共生型サービスの周知・啓発を図り、利用促進します。
- 既存の市営住宅の有効活用を図る中で、障がい者向け住宅を確保する等、障がい者の立場に立った良好な住環境を整備します。
- 障がい者の地域での自立生活や障がい者の地域移行を支援するため、関係機関と連携し、グループホームの充実を図ります。
(2)障がい者及び家族介護者等への生活支援
【現状と課題】
障がい者が地域社会で自立した生活を営むためには、経済的基盤の安定が重要です。
そのためには、障がいの重度化・重複化及び障がい者本人やその介護者の高齢化、経済動向等を考慮する中で、医療費の負担軽減や年金等の所得保障の充実といった、経済的な支援をする必要があります。
また、障がい者本人やその介護者の高齢化が進む中、障がい者を介護する家族の負担が大きくなっています。重度障がい者も含め、障がい者が地域で安心した生活を送るためには、障がい者を日常的に介護している家族等への支援が重要となります。
家族だけで負担を抱え込んだり、地域で孤立したりするようなことがないように、必要なときに気軽に利用できる一時預かり(レスパイトサービス)を始め、適切な支援を充実させていく必要があります。
【具体的取組】
- 各種の広報媒体を活用し、医療費の自己負担分への助成や障がい者が受け取ることができる年金のほか、特別障害者手当等の制度を広く周知します。
- 障がい者の生活の安定を図るため、県の心身障害者扶養共済制度を周知するとともに、掛金を助成します。
- 自動車税やNHKの受信料の減免等、各種の制度を周知するとともに、対象範囲の拡大を関係機関へ要望します。
- 障がい者に対する軽自動車税の減免について、周知・啓発に努めます。
- 障がい者の自立のため、県社会福祉協議会が実施主体となっている生活福祉資金貸付事業を周知するとともに、利用を促進します。
- 障がい者を介護する家族等が、介護の悩みの相談や情報交換を行う等、交流する機会の充実に向けた支援を行うとともに、障がい者団体の取組を支援します。
- 障がい者本人やその家族が、相互に援助を行う活動であるピアカウンセリング等への支援を行います。
- 障がい者やその家族を地域で見守る体制づくりや、短期入所等(レスパイトサービス)の普及を図ります。
- 障がい者を介護する家族等が窓口で相談しやすい環境の整備を行います。
(3)雇用の啓発と関係機関との連携
【現状と課題】
雇用・就労は、障がい者の自立や社会活動への参加のために重要であり、障がい者が能力を発揮し、働くことによって社会に貢献できるよう、雇用環境を整備することが求められています。
企業への障がい者雇用の啓発を始め、障がい者に対する職業訓練や事業所に対する助成、職場定着までの相談や支援等、様々な施策が国や県等で行われていますが、障がい者雇用率は十分ではなく、就職先が見つからなかったり、一般就労に就けてもなかなか定着ができないケースも多くあります。新型コロナウイルス感染症の影響による雇止めの問題も、障がい者雇用に影響を及ぼすことが予想されます。
なお、近年、いわゆる「農福連携」として、障がい者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の安定や発展とともに、障がい者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組が各地で展開されています。農業の担い手不足等の地域課題解決にもつながる「ウィン・ウィン(Win-Win)」の取組として、農福連携をさらに推進することが求められています。
【具体的取組】
- 障がい者の雇用に対する市民や企業の理解を深めるため、公共職業安定所(ハローワーク)等の関係機関と連携し、啓発活動を行います。
- 障がい者が働くための職場環境の整備等、障がいに対する合理的配慮についての啓発を行います。
- ハローワーク、県、香川障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、学校等と連携し、障がいの種別や程度、能力や適性に応じた効果的な職業相談等の実施を促進します。
- 本市や県内での農福連携の取組事例を市ホームページで紹介する等、農福連携の更なる普及に向けた啓発活動を行います。
- 市役所内障がい者就労の場「ヨロコビ たかまつ ふれあいの店」で、農業を行う障害福祉サービス事業所が生産した加工食品等を販売します。
(4)一般就労の促進
【現状と課題】
香川労働局発表の障がい者雇用率(令和元年6月1日現在)は、香川県で平均2.05%と、前年より上回ったものの、民間の法定雇用率(同日現在2.2%)及び全国平均(2.11%)を下回っており、障がい者の雇用は十分な状況とはいえません。新型コロナウイルス感染症の拡大が社会に影響を及ぼし始めた令和2年2月以降、失業者数・失業率は上昇しており、その先行きが見通せない中、民間の障がい者雇用に対する姿勢の後退が懸念されます。
障がい者の一般就労においては、就労移行支援等のサービスの充実、就労・生活支援センター等における就労に関する情報提供や相談支援等、雇用・就労における総合的な支援体制づくりに取り組むとともに、障がい者の能力に応じた職域の拡大や障がい者が働きやすい多様な雇用形態・就業形態の促進等、安定した雇用促進に向けた支援策の充実が求められています。これらの取組は、本市における障がい者の雇用についても同様に必要です。
【具体的取組】
- 障がい者の雇用の拡大を図るため、障がい者の法定雇用率や、法定雇用率を満たさない場合の雇用納付金制度及び雇用促進のための国・県が行う各種助成金制度や、その他の支援制度について、企業へ周知・啓発します。
- ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等と連携して、障がい者の就労支援について総合的な情報提供、相談援助等を行います。
- 障がい者の雇用が効果的に進められるように、短時間勤務や在宅勤務といった、多様な勤務形態の確立を目指し、関係機関と連携して普及啓発を行うとともに、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用を促進します。
- 障がい者の就労能力の向上と職域の拡大を図るとともに、就労生活を支えるグループホーム等の充実を図ります。
- 就労移行支援事業所等への支援を通じて、一般就労の促進を図るとともに、障がい者の就労支援に関して基盤の充実を図ります。
- 本市における障がい者の雇用では、一般職員の募集と併せて、障がい特性に応じた業務に従事する職員募集を行う等、障がい特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫し、知的障がい者、精神障がい者及び重度身体障がい者の積極的な採用に努めます。また、障がいのある職員を対象としたアンケートを毎年度実施し、障がい者と業務の適切なマッチングができているかの点検を行い、必要に応じて検討を行い、改善につなげます。
(5)福祉的就労の場の確保と充実
【現状と課題】
一般就労として雇用されることの難しい障がい者が、就労の機会を得られ、作業や生産活動に携わることのできる就労継続支援事業や地域活動支援センター等の役割は、障がいの重度化・重複化傾向と特別支援学校卒業者の増加に伴い、ますます重要となっており、アンケートやグループインタビューにおいても、就労・雇用について必要なこととして「就労継続支援A型事業所の増加」や「就労支援サービスの充実」が求められています。
今後も、その需要に応じた事業所の整備を促進するとともに、事業の安定運営や工賃の向上等を図っていくことが求められています。
また、障がい者の社会的自立を支援するため、国の障害者雇用納付金や障がい者雇用のための各種助成措置を周知するとともに、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)に基づき、本市が率先して、障害者就労施設等からの調達を拡充していくことが必要です。
【具体的取組】
- 関係機関と連携しながら、就労継続支援事業所や地域活動支援センター等が供給する物品等の販売を促進します。
- 障害者優先調達推進法を踏まえ、本市における物品等の調達の拡充を図ります。
- 就労継続支援事業所や地域活動支援センター等に対して、物品等の品質向上や販売促進等、事業の安定運営と工賃の向上につながる支援を行います。